2025年秋に放送された「林修の今知りたいでしょ!7つの新習慣SP」をご覧になりましたか?
番組では、私たちの健康寿命を延ばすための、今日から始められる新しい習慣が多数紹介され、大きな話題を呼びました。
この記事では、番組で取り上げられた、血圧にいい新・ウォーキング習慣!や睡眠にいい新・睡眠習慣!、さらには肩こり・腰痛にいい新ストレッチ習慣!まで、7つの重要な健康法を徹底的に解説します。
足腰にいい新筋トレ習慣!、血糖値にいい新・食べ方習慣!、血管にいい新・お風呂習慣!、そして心肺機能を高める新・呼吸習慣!に関する専門家の知識を、見逃してしまった方や、もう一度内容を確認したい方のために分かりやすくまとめました。
あなたの明日を健やかに変えるヒントが、ここにあります。
この記事のポイント
- 番組で紹介された7つの新習慣の概要
- 各健康法の具体的なやり方とポイント
- 専門家が解説する健康習慣の注意点
- 日常生活にすぐ取り入れられる実践的なコツ
「林修の今知りたいでしょ!7つの新習慣SP」概要
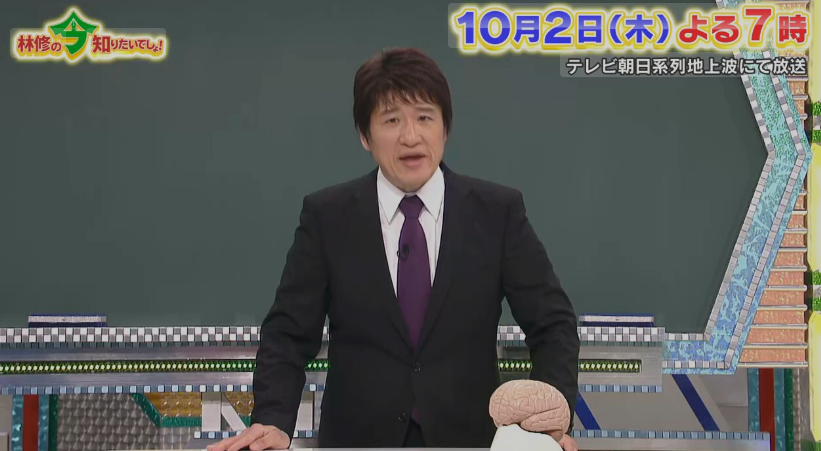
- ①血圧にいい「新・ウォーキング習慣!」を解説
- ②睡眠にいい「新・睡眠習慣!」で認知機能アップ
- ③肩こり・腰痛にいい「新ストレッチ習慣!」の方法
- ④足腰にいい「新筋トレ習慣!」で健康寿命を延ばす
- ⑤血糖値にいい「新・食べ方習慣!」とは
①血圧にいい「新・ウォーキング習慣!」を解説
2日(木)よる7時からの#林修の今知りたいでしょ は#林修 還暦でしょ
血圧・血糖値・肩こり…専門家7人が教える7つの新習慣3時間SP🌟🟡#timelesz #松島聡 さんも実践❇️ウォーキング法🚶♂️
🟡柳沢先生が教える‼️もの忘れを防ぐ睡眠法😴#バカリズム #筒井真理子 #星野真里 #伊沢拓司 #白洲迅 #猪俣周杜 pic.twitter.com/qSjuHVX7Ww— 【公式】林修の今知りたいでしょ! (@imadesyo_ex) September 30, 2025
血圧対策として手軽に始められるのがウォーキングです。
特に推奨されるのが「インターバル速歩」と呼ばれる方法で、信州大学の能勢博先生らが提唱しています。
これは、単に長時間歩くよりも高い運動効果が期待できるウォーキング法です。
インターバル速歩の具体的なやり方
インターバル速歩は、「早歩き」と「ゆっくり歩き」を数分間ずつ交互に繰り返すのが特徴です。
具体的には、「早歩き3分、ゆっくり歩き3分」を1セットとし、これを1日に5セット(合計30分)行うのが基本とされています。
早歩きの際は、やや大股で、息が少し弾む程度のスピードを意識します。
この運動を週に4日程度行うことで、筋力や持久力が向上し、血圧の安定化や生活習慣病の予防に繋がると考えられています。
インターバル速歩の注意点
運動を始める前には、必ず準備運動を行いましょう。
また、膝や腰に痛みがある方は無理をせず、かかりつけの医師に相談することをおすすめします。
自分の体力に合わせて、時間やセット数を調整することが大切です。
②睡眠にいい「新・睡眠習慣!」で認知機能アップ
番組で最初に注目されたのが、睡眠の「時間」だけでなく「規則性」が重要であるという点です。
睡眠学の世界的権威である柳沢正樹先生によると、寝る時間と起きる時間を一定に保つ人は、そうでない人に比べて認知機能が高いという研究結果が報告されています。
その理由は、私たちの脳に備わっている体内時計のリズムと、実際の生活リズムが常に一致することにあります。
このリズムが整うと、脳の神経細胞にとって肥料のような役割を果たす脳内物質「BDNF」の分泌が促されることが分かってきました。
睡眠が規則的な人ほど、このBDNFの値が高い傾向にあり、これが認知機能の高さに関与していると考えられています。
新・睡眠習慣のポイント
番組では、理想的な睡眠習慣として以下の2点が挙げられました。
- 就寝・起床時間
毎日のズレをプラスマイナス30分以内(合計1時間以内)に収める - 理想の睡眠
レム睡眠が4回訪れるよう、最低でも6時間半程度の睡眠時間を確保する
タレントの青木さやかさんが挑戦した検証では、普段より30分早く寝ることを習慣づけた結果、熟睡感の指標となるレム睡眠の回数が増加しました。
寝つきを良くするためには、寝る1時間前にはスマートフォンや台本チェックなど脳を活性化させる活動をやめ、リビングなどでリラックスする時間を作ることが推奨されています。
「寝る前にスマホを見てしまう」という方は多いのではないでしょうか。
番組では、その行為が脳を覚醒させ、寝つきを悪くする原因になると指摘されていました。
寝室は「リラックスして眠る場所」と脳に覚えさせることが、質の高い睡眠への第一歩です。
③肩こり・腰痛にいい「新ストレッチ習慣!」の方法
多くの人が悩む肩こりや腰痛。その原因は、全身をボディスーツのように覆っている「ファシア」という組織の癒着にある可能性が指摘されています。
整形外科医の髙平信先生によると、長時間同じ姿勢でいることなどでファシアが硬く癒着すると、体の動きが制限され、痛みやコリに繋がるのです。
この癒着を解消するために番組で紹介されたのが「ファシア伸ばしストレッチ」です。
たった1回でも体の柔軟性に変化が現れる即効性が特徴で、スタジオの林修先生や井沢拓司さんもその効果に驚いていました。
4種類のファシア伸ばしストレッチ
番組で紹介された4つのストレッチを表にまとめました。それぞれ20秒キープが基本です。
| ストレッチ名 | ターゲット | 主な効果が期待できる症状 | 簡単なやり方 |
|---|---|---|---|
| バルーンストレッチ | バックライン(上半身) | 肩こり | 両手を組んで輪を作り、背中を丸めながら頭を入れ、手を前に突き出す。 |
| ハムストリングストレッチ | バックライン(下半身) | 腰痛 | アキレス腱を持ち、お腹と太ももをつけたまま膝を伸ばしお尻を上げる。 |
| とんがり体操 | フロントライン | 肩こり・腰痛 | 片足を大きく前に踏み出し、両手を真上に伸ばして斜め上を見る。 |
| ラテラルラインストレッチ | ラテラルライン(側面) | 肩こり | 足をクロスさせ、伸ばしたい側の手を反対の手で引っ張りながら体を横に倒す。 |
このストレッチは、1日1セットでも毎日続けることが重要です。
継続しないとファシアは再び癒着し、元の状態に戻ってしまうため、日々の習慣にすることが大切だと髙平先生は語っています。
④足腰にいい「新筋トレ習慣!」で健康寿命を延ばす
足腰の筋力は、健康寿命に直結する非常に重要な要素です。
きつい運動は続かないという方におすすめなのが、ゆっくりとした動作で行う「3秒筋トレ」です。
番組で紹介された習慣ではありませんが、日常生活の中で手軽に実践できるため、ここでご紹介します。
代表的なものに「椅子座り」があります。これは、椅子から立ち上がり、再び座る動作を極力ゆっくり行うトレーニングです。
特に、お尻が椅子に着くまでの最後の3秒間を意識して、ゆっくりと座ることで、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)に効果的に負荷をかけることができます。
3秒筋トレのバリエーション
他にも、「つま先立ちから3秒かけてかかとを下ろす」運動や、「片足を上げながら両手で膝を3秒間押す」運動など、様々なバリエーションがあります。
いずれも1日に10回程度を目安に行うと良いとされています。
これらのトレーニングは、テレビを見ながらでも実践できる手軽さが魅力です。
無理のない範囲で継続し、転倒しにくい丈夫な足腰を目指しましょう。
⑤血糖値にいい「新・食べ方習慣!」とは
糖尿病治療の名医である小田原雅人先生が解説したのは、よく噛むことの重要性です。実は、よく噛むことで、血糖値を下げるホルモン「GLP-1」が分泌されやすくなることが研究で明らかになっています。
GLP-1は、インスリンの分泌を促し、血糖値を上げるホルモンを抑制するという、2つの働きを持つ重要な物質です。
このホルモンの分泌を促す最も簡単な方法が、「噛む回数」を増やすことなのです。
噛む回数を自然に増やす3つのコツ
- 咀嚼回数の多い食材を取り入れる
アーモンドなどのナッツ類や、さきいか、ごぼうなど、歯ごたえのある食材を食事に加える。 - 食材を大きめに切る
カレーやきんぴらごぼうなどの具材を普段より大きく切るだけで、自然と噛む回数が増えます。 - 野菜は繊維に沿って切る
キャベツや玉ねぎなどを繊維に沿って切ると、シャキシャキ感が残り、咀嚼を促します。
フリーアナウンサーの中村仁美さんの検証では、これらの工夫を取り入れた食事を摂ることで、食後の血糖値の急上昇が大幅に抑制されるという結果が出ました。
厚生労働省は一口30回を目標に掲げていますが、まずはいつもの2倍噛むことを意識するだけでも効果が期待できます。
サバ缶もGLP-1の分泌を促進
番組では、サバなどの青魚に多く含まれるEPAも、GLP-1の分泌を刺激することが紹介されました。
特にサバ缶は手軽にEPAを摂取できるため、おすすめの食材です。
「林修の今知りたいでしょ!7つの新習慣SP」実践編
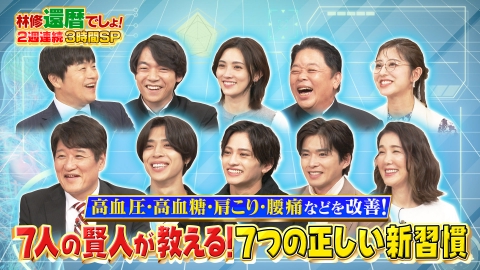
- ⑥血管にいい「新・お風呂習慣!」で血行促進
- ⑦心肺機能を高める「新・呼吸習慣!」のポイント
- 各習慣を実践する上での注意点
- 専門家が推奨する健康習慣のコツ
- まとめ:林修の今知りたいでしょ!7つの新習慣SP
⑥血管にいい「新・お風呂習慣!」で血行促進
夏のダメージをリカバーするためにおすすめなのが、お風呂にしっかり浸かることです。
入浴は血流を増加させ、血管壁を刺激することで、血管を柔らかくする物質「NO(一酸化窒素)」の分泌を促します。
東京都健康長寿医療センターの原田和昌先生が推奨するのは、この効果をさらに高める「お風呂グーパー」という新習慣です。
やり方は非常にシンプルで、湯船に浸かりながら、手のひらをグーパーと繰り返すだけです。
お風呂グーパーの正しいやり方
手を強く握ると手が白くなり、パッと開くと赤くなります。この血流が一気に流れる瞬間に、NOが多く分泌されます。ポイントは以下の2つです。
- 握る強さ
最大で握った時の3分の1程度の力で十分です。 - 繰り返すタイミング
パーにして白くなった手が、赤みが戻ってきてから再びグーにする。早すぎない、程よいスピードで行いましょう。
フリーアナウンサーの富永美樹さんの検証では、この習慣を1週間続けたところ、血管年齢が実年齢より若返り、高めだった血圧にも良い変化が見られました。
肩までしっかり浸かって水圧をかけることで、より効果が高まるとされています。
長風呂には注意
この習慣は手軽で効果も期待できますが、長風呂は脱水症状を引き起こす可能性があります。
入浴前後の水分補給を忘れずに行いましょう。
⑦心肺機能を高める「新・呼吸習慣!」のポイント
「階段を上るだけで息が切れる」と感じることはありませんか?その原因は、加齢による呼吸筋の衰えかもしれません。
呼吸器専門医の平松組子先生によると、肺は自力で動いているのではなく、横隔膜などの呼吸筋によって動かされています。
この筋肉が衰えると、心配機能も低下してしまうのです。
番組では、この呼吸筋をストレッチでほぐし、肺の機能を改善させる「新・呼吸習慣」が紹介されました。
簡単な3つのストレッチで、気になる息切れの軽減が期待できます。
3つの呼吸筋ストレッチ
- 肋骨の間の筋肉を伸ばすストレッチ
腰の後ろで手を組み、息を吐きながら腕を下に伸ばし、胸を張る。これを5回繰り返します。 - 背中の筋肉を伸ばすストレッチ
胸の前で両手を組み、息を吸いながら腕を前に伸ばす。息を吐きながら元の姿勢に戻ります。 - 首の筋肉を伸ばすストレッチ
肩の力を抜き、息を吸いながらゆっくりと顔を横に向ける。息を吐きながら正面に戻します。
実際にやってみると、胸の周りが広がり、深く息が吸えるような感覚があります。
特にデスクワークで同じ姿勢が続きがちな方には、仕事の合間のリフレッシュとしてもおすすめです。
これらのストレッチを習慣にすることで、呼吸筋の可動域が広がり、心配機能の向上が見込めます。
無理のない範囲で、日々の生活に取り入れてみましょう。
各習慣を実践する上での注意点
番組で紹介された7つの新習慣は、いずれも健康増進に役立つものですが、実践する際にはいくつか注意点があります。
まず、最も大切なのは「無理をしないこと」です。
例えば、新筋トレ習慣や新ストレッチ習慣は、膝や腰に痛みがある場合は悪化させる可能性があります。
必ず痛みのない範囲で行い、不安な場合は医師や専門家に相談してください。
また、新ウォーキング習慣も、その日の体調に合わせて距離や時間を調整することが重要です。
食事や入浴に関する習慣も同様で、アレルギーや持病がある方は、自己判断で極端な変更を加えるのは避けるべきです。
すべての習慣において、ご自身の体と対話しながら、心地よく続けられる範囲で取り入れることが、成功への鍵となります。
専門家が推奨する健康習慣のコツ
新しい習慣を長続きさせるには、いくつかのコツがあります。
番組に出演した専門家たちの言葉から、そのポイントを読み解くことができます。
一つ目は「ハードルを下げること」です。
例えば、「毎日30分歩く」と決めるのではなく、「週に4日から始める」「1日15分でもOK」と、達成しやすい目標を設定することが継続に繋がります。
ファシア伸ばしストレッチも、「1日1セットだけでも毎日行う」ことが重要だとされていました。
二つ目は「現在の生活スタイルに組み込むこと」です。
新しく時間を確保するのではなく、「テレビを見ながら筋トレをする」「お風呂に入りながらグーパー体操をする」など、”ながら”で出来る習慣は長続きしやすい傾向にあります。
完璧を目指さないことも大切ですね。
週に数日できなくても、「また明日からやろう」と気楽に構えることが、習慣化を成功させる秘訣だと感じました。
最後に、「効果を実感すること」も大きなモチベーションになります。
体の変化を楽しみながら、ぜひこれらの新習慣にチャレンジしてみてください。
「林修の今知りたいでしょ!7つの新習慣SP」総まとめ
この記事では、「林修の今知りたいでしょ!7つの新習慣SP」で紹介された健康法を詳しく解説しました。
最後に、番組で紹介された7つの新習慣の要点をリスト形式でおさらいします。
- 睡眠は時間だけでなく規則性が認知機能に重要
- 就寝と起床時間のズレは1時間以内に収めるのが理想
- 寝る1時間前はスマホなどをやめリラックスタイムを設ける
- 肩こりや腰痛の原因は全身を覆うファシアの癒着
- ファシア伸ばしストレッチは1日1セットでも毎日継続することが大切
- 息切れは肺を動かす呼吸筋の衰えが原因の可能性がある
- 呼吸筋ストレッチで肺の可動域を広げ心肺機能の向上が期待できる
- 血糖値対策にはよく噛むことが効果的
- 噛むことで血糖値を下げるホルモンGLP-1の分泌が促される
- 食材を大きく切るなど工夫して噛む回数を増やす
- サバ缶に含まれるEPAもGLP-1の分泌を助ける
- 入浴時に手をグーパーすると血管を柔らかくするNOが分泌される
- グーパー体操は3分の1程度の力で程よいスピードで行う
- 新しい習慣は無理せず自分のペースで続けることが最も重要
- ハードルを下げて日常生活に組み込むのが継続のコツ
最後までお読み頂きありがとうございます♪



