「ホンダのロケット開発ってどうなの?」「海外ではどんな反応なんだろう?」と気になっていませんか。
自動車メーカーとして知られるホンダが、2025年6月にロケットの垂直離着陸実験に成功したというニュースは、多くの人々を驚かせました。
この成功は、単なる技術デモではありません。
ホンダのロケットへの海外の反応は称賛と驚きに満ちており、H3成功で盛り上がる日本のロケットへの海外の反応とはまた違った形で、日本の技術力を世界に示しました。
この記事では、読者の皆様が抱くであろう「ホリエモンはどう評価している?」
「成功の鍵となった精密な離着陸技術や、選択された燃料、心臓部であるターボポンプの詳細は?」
「次の拠点は和歌山にも?」
「そもそもホンダはロケット開発に注力するのでしょうか?」
といった疑問に、分かりやすくお答えします。
さらに、事業戦略の背景にあるホンダの海外比率はどのくらいか、開発を支えるホンダの平均年収はいくらか、そして最も気になるホンダのロケットの今後はどうなりますか、という点まで、専門的な情報を基に徹底的に掘り下げていきます。
この記事でわかること
- ホンダのロケット技術の凄さと海外からの具体的な評価
- 自動車メーカーであるホンダが宇宙開発に参入した戦略的な理由
- 日本の宇宙産業におけるホンダの立ち位置と競合との比較
- ホンダのロケット開発が目指す2029年までの目標と今後の課題
技術的快挙とホンダロケットへの海外の反応
- ①驚異的な精度を誇る離着陸技術
- ②再使用に適したメタン燃料の選択
- ③開発の鍵を握るターボポンプ
- ④ホリエモンも高く評価する技術力
- ⑤日本ロケット海外の反応との違い
①驚異的な精度を誇る離着陸技術
 イメージ
イメージ
ホンダのロケット実験が世界を驚かせた最大の理由は、その驚異的な着陸精度にあります。
2025年6月17日に行われた実験では、機体は目標着地点からわずか37cmというピンポイントでの着陸に成功しました。
これは、再使用型ロケットの実現において最も重要かつ困難な技術の一つです。
この技術の根底には、ホンダが長年培ってきたロボット工学と自動運転技術があります。
例えば、二足歩行ロボット「ASIMO」の開発で磨かれた姿勢制御技術や、自動運転システムで培われた高度な誘導制御が、ロケットの垂直離着陸(VTVL)に応用されているのです。
まさに、数十年にわたる異分野の研究開発が、宇宙という新たなステージで花開いた瞬間と言えます。
自動車メーカーが持つ「動くモノを精密にコントロールする技術」という遺産が、これほど高いレベルで発揮されたことは、多くの専門家にとって大きな驚きでした。
もちろん、今回の実験は高度約271mの低高度での成功であり、宇宙空間からの帰還とは環境が大きく異なります。
しかし、この初期段階での高い完成度は、ホンダの技術開発能力が本物であることを証明しており、今後の開発への期待を大きく膨らませる結果となりました。
②再使用に適したメタン燃料の選択
 イメージ
イメージ
ホンダが実験機に採用した燃料は、液体酸素と液体メタンを組み合わせた、通称「メタンロックス」です。
この燃料選択は、プロジェクトが当初から「再使用」を大前提としていることを示す、非常に戦略的な判断といえます。
メタン燃料には、主に以下の3つの大きなメリットがあります。
1. 再使用性への適合
メタンは燃焼時に「煤(スス)」の発生が非常に少ないという特徴があります。
これは、エンジンの洗浄やメンテナンスを容易にし、打ち上げから次の打ち上げまでのターンアラウンドタイムを大幅に短縮できることを意味します。
再使用の頻度を高め、コストを削減する上で極めて重要な要素です。
2. コストと入手性
一般的に、従来主流だったケロシン燃料よりも安価です。
さらに、将来的には火星の大気などから現地で製造できる可能性も示唆されており、地球外での活動も視野に入れた際の持続可能性が高い燃料と言えるでしょう。
3. 性能
メタンはケロシンよりも高い「比推力(ひすいりょく)」を持ちます。
これは、いわば「燃費の良さ」を示す指標であり、より少ない燃料で大きな推進力を得られることを意味します。
機体の小型化や、より重いペイロード(荷物)の搭載に繋がります。
補足:ホンダはこの燃料システムを「持続可能燃料システム」と位置づけています。
これは、環境負荷と運用コストの両面を考慮した、長期的な視点に立った技術選択であることを示しています。
このように、燃料一つをとっても、ホンダの宇宙開発が単なる一過性のプロジェクトではなく、持続可能な宇宙輸送システムの構築を目指す、計算された戦略に基づいていることが分かります。
③開発の鍵を握るターボポンプ
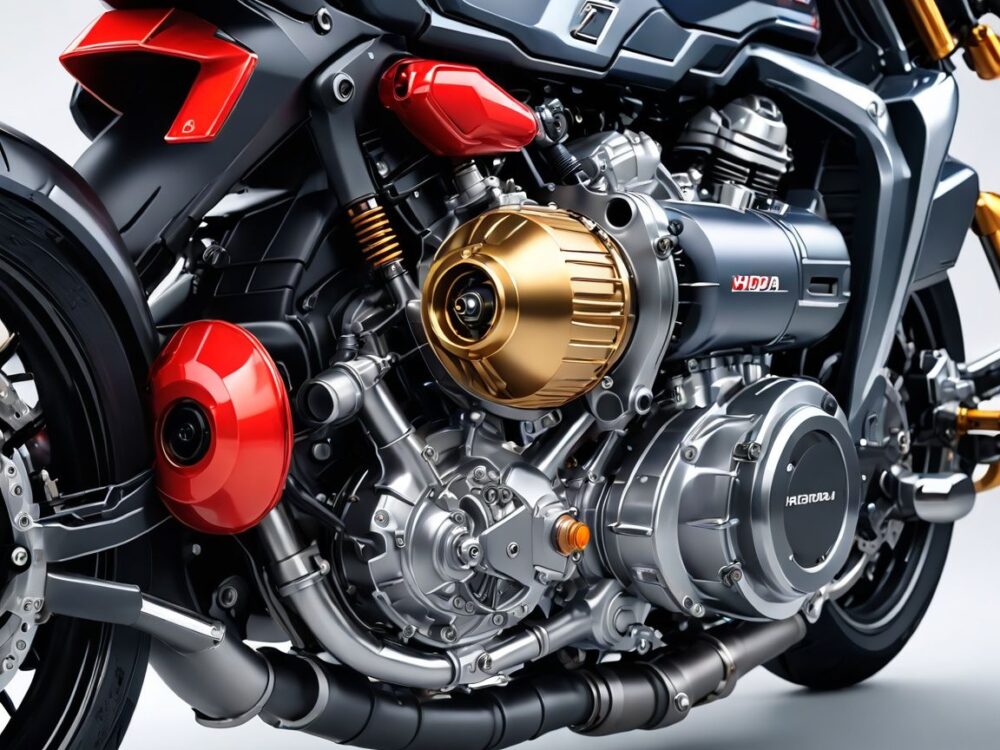 イメージ
イメージ
ロケットエンジンの「心臓部」と称されるほど、極めて重要で開発が難しい部品が「ターボポンプ」です。
これは、燃料と酸化剤を燃焼器へ高圧で送り込むための装置であり、その性能がエンジン全体の能力を決定づけると言っても過言ではありません。
ターボポンプの開発には、超高速で回転するタービンや、極低温の液体を扱う高度な技術力が要求されます。
そのため、多くの新規参入企業にとって最大の壁の一つとなっています。
日本の民間宇宙企業であるインターステラテクノロジズ(IST)も、ターボポンプの自社開発に成功しましたが、その過程の困難さを強調しています。
これは、大手重工メーカー以外では非常に稀なケースであり、ターボポンプを制することがロケット開発を制すると言われる所以です。
ホンダが今後、より強力なエンジンを開発し、準軌道、そして軌道上へと到達するためには、このターボポンプのさらなる高性能化が避けては通れない道となるでしょう。
④ホリエモンも高く評価する技術力
 イメージ
イメージ
日本の民間宇宙開発の先駆者であり、インターステラテクノロジズ(IST)の創業者でもある実業家の堀江貴文(ホリエモン)氏も、ホンダのロケット開発に注目し、高く評価するコメントを発信しています。
堀江氏は自身のSNSやVoicyなどで、ホンダの成功について「すでに再使用技術を手に入れたと言ってもいい」と、その技術レベルを称賛しました。
特に、初回の公開実験であれだけの精密な着陸を成功させた制御技術には、驚きを示しています。
ただ、称賛するだけでなく、冷静な分析も加えています。
堀江氏は「大型化しない限りコスト低減効果は限定的」とも指摘しており、現在の実験機のサイズから商業ベースに乗せるまでのスケールアップが今後の大きな課題になるとの見方を示しました。
これは、宇宙ビジネスの現実を知る当事者ならではの鋭い視点と言えます。
このように、同じ業界で開発競争を行うライバルからも称賛と期待の声が上がることは、ホンダの挑戦がいかにインパクトの大きいものであったかを物語っています。
ホンダの参入は、ISTをはじめとする国内の民間企業にとっても、業界全体を盛り上げる大きな刺激となっているのです。
⑤日本ロケット海外の反応との違い
 イメージ
イメージ
「日本のロケットに対する海外の反応」という点で、今回のホンダの成功と、日本の基幹ロケットであるH3ロケットの事例を比較すると、非常に興味深い違いが見えてきます。
H3ロケットは、日本の威信をかけた国家プロジェクトです。
そのため、2023年の初号機打ち上げ失敗は「日本の宇宙への野心への打撃」として世界で大きく報じられ、日本の技術力に対する信頼を揺るがす事態となりました。
その後の2号機成功は「見事なカムバック」として評価されましたが、そこには常に失敗からの回復というストーリーが伴います。
対するホンダの物語は全く異なります。
民間企業であるホンダには、国家の威信というプレッシャーはなく、世間の期待値はゼロに近い状態でした。
そこからの「サプライズ成功」は、純粋に企業の技術力と創意工夫を称える「アンダードッグ(挑戦者)の勝利」として、極めて好意的に受け止められたのです。
海外メディアは「日本の巨大自動車メーカーが自動運転技術を応用して宇宙へ」といった切り口で、この異業種からの挑戦を驚きをもって伝えました。
H3の物語が「苦闘と回復」であるのに対し、ホンダの物語は「驚きと卓越した能力」として映ったのです。
この対比は、国家主導の巨大プロジェクトとは異なる、民間企業によるイノベーションが持つ「ソフトパワー」の重要性を示しています。
ホンダは意図せずして、日本の技術力に対する国際的な評価を、H3とは別の角度から高める役割を果たしたと言えるでしょう。
深掘り!ホンダロケットへの海外の反応の背景
- ①ホンダはロケット開発に注力するのでしょうか?
- ②8割を超えるホンダの海外比率は?
- ③技術を支えるホンダの平均年収は?
- ④次なる拠点は和歌山になる可能性
- ⑤ホンダのロケットの今後はどうなりますか?
- ⑥まとめ:ホンダロケットへの海外の反応
①ホンダはロケット開発に注力するのでしょうか?
 イメージ
イメージ
「自動車メーカーのホンダが、なぜ今ロケットなのか?」これは多くの人が抱く最大の疑問でしょう。
公式には、このプロジェクトはまだ「要素研究の段階」であり、事業化が決定しているわけではない、とされています。
しかし、その一方で、2029年までに準軌道への到達能力を実現するという明確な目標を掲げ、北海道に専用の実験施設を建設し、アメリカにも宇宙開発部門を設立するなど、その動きは単なる研究の域を超えているように見えます。
この挑戦の背景には、打ち上げ機そのものの開発に留まらない、ホンダの広範な宇宙戦略が存在します。
- 循環型再生エネルギーシステム
JAXAと共同で、月面で電力や酸素を供給するシステムを研究。 - 衛星への燃料補給
アストロスケール社と提携し、軌道上サービス技術を開発。 - アバターロボット
ASIMOの技術を応用し、月面などで遠隔作業を行うロボットを開発。
結論として、ホンダはロケット開発に真剣に注力していると考えられます。
ロケットは、これらの未来の宇宙事業に必要な物資や機材を自社で運ぶための「輸送手段」として位置づけられているのです。
これは、自社の事業を根幹から支えるための、非常に長期的な視点に立った先行投資と言えるでしょう。
②8割を超えるホンダの海外比率は?
 イメージ
イメージ
ホンダのロケット開発の動機を理解する上で、非常に重要な鍵となるのがグローバル企業としての側面です。
ホンダは「日本の自動車メーカー」であると同時に、その収益の大部分を海外市場に依存しています。
具体的に、ホンダの海外売上比率は、実に8割を超えています。
この事実は、同社の事業が世界中の物流、販売、そして通信ネットワークに支えられていることを意味します。
本田技研工業株式会社 – 事業エリア別売上構成
| エリア | 売上比率(参考値) | 意味合い |
|---|---|---|
| 海外合計 | 約83% | 収益の大部分を海外に依存 |
| 北米 | 約42% | 最大の市場であり最重要エリア |
| アジア | 約22% | 成長を牽引する重要市場 |
| 日本 | 約17% | 研究開発の基盤だが売上比率は低い |
(出典:各種公開情報に基づき作成)
ここで重要になるのが、コネクテッドカーや自動運転といった次世代技術です。
これらの技術は、高精度な位置情報やデータ通信を担う人工衛星なしには成り立ちません。
現状、その衛星打ち上げはSpaceXなど少数の海外企業に依存しており、これはホンダにとって将来的なビジネス上の大きなリスクとなり得ます。
もし打ち上げコストが高騰したり、サービスが利用できなくなったりすれば、主力製品の競争力が根底から揺らぐ可能性があるのです。
つまり、ホンダのロケット開発は、新たな市場を開拓する「攻め」の一手であると同時に、自社の主力事業の未来を守るための「戦略的な防衛」でもあるのです。
高い海外売上比率こそが、自社で宇宙へのアクセス手段を持とうとする強力な動機になっているわけです。
③技術を支えるホンダの平均年収は?
 イメージ
イメージ
これほど高度で長期的な研究開発を支えるには、優秀な人材の確保と維持が不可欠です。
その基盤となるのが、企業の体力と従業員の待遇です。
ホンダの平均年収は、その企業としての実力を示す一つの指標となります。
有価証券報告書などの公開情報によると、本田技研工業の2024年3月期における平均年間給与は約831万円とされています。
これは日本の製造業全体の中でも非常に高い水準です。
この高い給与水準は、ロケット開発のような最先端分野で活躍するトップクラスのエンジニアや研究者を惹きつけ、定着させるための強力な武器となります。
また、潤沢な研究開発費と合わせて、社員が目先の利益に囚われず、ASIMOやHondaJet、そして今回のロケットのような長期的で挑戦的なプロジェクトに集中できる環境を生み出していると言えるでしょう。
企業の財務的な安定と、それによってもたらされる人材への投資こそが、一見すると本業からかけ離れた宇宙開発という壮大な挑戦を可能にする、隠れた原動力となっているのです。
④次なる拠点は和歌山になる可能性
 イメージ
イメージ
現在、ホンダがロケットの燃焼試験や飛行実験を行っている拠点は、北海道広尾郡大樹町です。
ここは「宇宙のまちづくり」を掲げ、インターステラテクノロジズ(IST)なども拠点を置く、日本の民間宇宙開発の聖地ともいえる場所です。
しかし、今後の開発フェーズ、特にロケットの大型化や打ち上げ頻度の向上を見据えた場合、新たな射場の確保が重要になってきます。
その候補の一つとして名前が挙がっているのが、和歌山県串本町です。
補足:スペースポート紀伊
和歌山県串本町には、日本初の民間ロケット射場である「スペースポート紀伊」が既に稼働しています。
ここは、主にスペースワン株式会社が固体燃料ロケット「カイロス」を打ち上げるために整備されました。
スペースポート紀伊は、南方に開けており、ロケットの打ち上げ方向に陸地や船舶航路が少ないという地理的なメリットがあります。
これは、より大型のロケットを安全に打ち上げる上で非常に有利な条件です。
もちろん、射点の規模拡大や周辺住民との合意形成など、クリアすべき課題は少なくありません。
しかし、ホンダが開発を本格化させていく中で、北海道の大樹町と並行して、和歌山のスペースポート紀伊も利用するという選択肢は十分に考えられます。
日本の民間宇宙開発は、複数の拠点がそれぞれの特徴を活かしながら連携していく、新たな時代に入りつつあります。
⑤ホンダのロケットの今後はどうなりますか?
 イメージ
イメージ
ホンダのロケット開発は、明確なロードマップに沿って進められています。
当面の最大の目標は、「2029年までに準軌道への到達能力を実現する」ことです。
準軌道飛行(サブオービタル飛行)とは、高度100km付近の宇宙空間には到達するものの、地球を周回する軌道には乗らずに地上へ帰還する飛行形態を指します。
これが実現すれば、以下のようなビジネス展開の可能性が拓けます。
- 微小重力実験サービス
科学研究や新素材開発のための安価な実験プラットフォーム。 - 技術実証の場
将来の軌道上サービスで使う機器の宇宙環境でのテスト。
今後の挑戦
ただし、2029年の目標達成、そしてその先の商業化への道のりは平坦ではありません。
高度数百メートルのホップ飛行から高度100kmへのスケールアップは、エンジン推力の大幅な向上や機体制御など、質的に異なる巨大な技術的課題を乗り越える必要があります。
また、顧客の荷物を載せるには、圧倒的な信頼性の証明が不可欠であり、経営判断として事業化に踏み切れるかどうかも大きな関門となります。
ホンダはまず、技術的ハードルが比較的低い準軌道飛行で実績を積み、ビジネスモデルを模索するでしょう。
そして、そこで得られた技術とノウハウを基に、2030年代には小型衛星を地球周回軌道へ投入する、より大型のロケット開発へとステップアップしていく可能性が高いと考えられます。
まとめ:ホンダロケットへの海外の反応
この記事では、ホンダのロケット開発に対する海外の反応から、その技術的な背景、企業の戦略、そして今後の展望までを詳しく解説しました。
最後に、本記事の要点をまとめます。
- ホンダは2025年6月にロケットの垂直離着陸実験に成功した
- 着陸誤差はわずか37cmで世界中の専門家から高い評価を得た
- 海外メディアは自動車技術の応用という異業種からの挑戦を驚きをもって報じた
- 成功の鍵はASIMOなどで培った精密な姿勢制御技術にある
- 燃料には再使用に適したメタンロックスを戦略的に採用している
- エンジンの心臓部であるターボポンプの開発が今後の鍵を握る
- ホリエモンは技術力を高く評価しつつ今後の大型化に期待を寄せた
- 国家プロジェクトのH3とは異なり民間のサプライズ成功として好意的に受け止められた
- 公式には研究段階だが2029年の準軌道到達という明確な目標がある
- ロケット開発は自社の宇宙事業を支えるための垂直統合戦略の一環である
- 8割を超える高い海外売上比率が自社インフラを持つ動機となっている
- 約831万円という高い平均年収が優秀な人材確保の基盤となっている
- 現在の拠点は北海道大樹町だが今後は和歌山も候補になる可能性がある
- 今後は準軌道飛行で実績を積み2030年代の軌道投入を目指すと予測される
- ホンダの挑戦は日本の宇宙産業全体を活性化させる起爆剤となる
最後までお読み頂きありがとうございます♪




